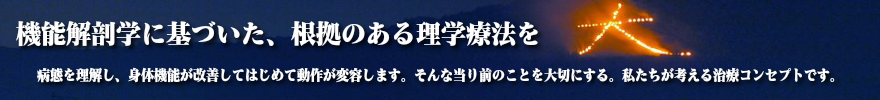前十字靭帯損傷に対するACLRを行う際、膝蓋腱とならび多く使用される膝屈筋腱、中でも半腱様筋腱や薄筋腱を用いたSTG法で行うケースが多々あると思われます。
そこで今回は、膝屈筋群採取後の再生様腱組織が術後どのように機能するかについて報告している文献を紹介したいと思います。
対象はSTG法にてACLRを行なった20膝で、視診・MRIにて採取部に再生様腱組織が確認された群を再生群、それ以外を非再生群とされており、術後経過期間は平均24ヶ月でありました。
これらの対象に対し、Cybexを用いて等速運動での膝屈筋力の最大トルク値、最大自動膝屈曲角度の対健側差(flexion lag)を測定し、両群の比較を行われていました。
結果は、最大トルク値では有意な差は認められず、flexion lagで非再生群は再生群に比べ有意に大きな値を示していました。
膝屈筋群の収縮形態は各々の筋でで異なり、半腱様筋は大腿二頭筋に比べ、より屈曲角度が大きいほど筋力が発揮しやすいとされています。
今回の結果から、最大トルク値が変わらないものの、再生群でflexion lagが有意に小さかった原因として、採取後も半腱様筋の収縮動態が術後も変わらず残存していることが考えられます。
また、再生した半腱様筋腱は本来の脛骨付着部とは異なり、近位側で下腿筋膜へ移行する様に再生することが他の文献でも紹介されていますが、今回紹介した文献の中では、より中枢側では正常とほぼ同等の走行を示し、術後も本来と同様の働きをすることが示唆されています。
術式やその後の組織修復過程を知っておくことは、術後理学療法を進めていく中でとても重要になると考えています。さらに、組織の動態を理解しておくことも必要不可欠です。
今後も、病態理解や術後理学療法を行う上で必要な知識を積み重ねていき、より良い理学療法を提供できるよう、努力していきたいと思います。
投稿者:高橋 蔵ノ助
そこで今回は、膝屈筋群採取後の再生様腱組織が術後どのように機能するかについて報告している文献を紹介したいと思います。
中村英一ら:膝屈筋腱を用いたACL再建術後の採取腱の再生と膝屈筋力について:整形外科と災害外科.50(1).130-133.2001
対象はSTG法にてACLRを行なった20膝で、視診・MRIにて採取部に再生様腱組織が確認された群を再生群、それ以外を非再生群とされており、術後経過期間は平均24ヶ月でありました。
これらの対象に対し、Cybexを用いて等速運動での膝屈筋力の最大トルク値、最大自動膝屈曲角度の対健側差(flexion lag)を測定し、両群の比較を行われていました。
結果は、最大トルク値では有意な差は認められず、flexion lagで非再生群は再生群に比べ有意に大きな値を示していました。
膝屈筋群の収縮形態は各々の筋でで異なり、半腱様筋は大腿二頭筋に比べ、より屈曲角度が大きいほど筋力が発揮しやすいとされています。
今回の結果から、最大トルク値が変わらないものの、再生群でflexion lagが有意に小さかった原因として、採取後も半腱様筋の収縮動態が術後も変わらず残存していることが考えられます。
また、再生した半腱様筋腱は本来の脛骨付着部とは異なり、近位側で下腿筋膜へ移行する様に再生することが他の文献でも紹介されていますが、今回紹介した文献の中では、より中枢側では正常とほぼ同等の走行を示し、術後も本来と同様の働きをすることが示唆されています。
術式やその後の組織修復過程を知っておくことは、術後理学療法を進めていく中でとても重要になると考えています。さらに、組織の動態を理解しておくことも必要不可欠です。
今後も、病態理解や術後理学療法を行う上で必要な知識を積み重ねていき、より良い理学療法を提供できるよう、努力していきたいと思います。
投稿者:高橋 蔵ノ助